スポンサードリンク
エドゥアール・マネ「オランピア」Olympia

この絵の前に立ったとき一番注意をひかれるのは、彼女のもの言いたげな眼差しです。目があうような、あわないような、あわせてはいけないような、そんな感覚を覚えます。
現代の日本に生きる私達には、 そこに描かれているのが、女神だろうが、生身の女性だろうが、裸の女の人であることに変わりはなく、どちらでも大差ないだろう…と思えます。
しかし、19世紀のパリでは事情が違いました。サロン(官展・絵画を発表する場)で、前例がないくらいに批判されたという「オランピア」。この絵のベースが、ルネサンスの巨匠・ティツィアーノ作「ウルヴィーノのヴィーナス」であることは明らかです。どうしてティツィアーノの女神は崇拝され、マネのオランピアは批判されなくてはならなかったのでしょうか。同じような構図の横たわる裸婦像ですが、しかし、マネが描いたのは娼婦でした。
この時代の前後までは、絵画に描かれる裸の女性といえば、理想としての美である「女神」が常識でした。
新しい傾向には、そうでなくても厳しいサロンで、裸の娼婦像が受け入れられるはずはなかったのです。
タイトル 「オランピア」は 当時の娼婦がよく用いた源氏名です。
他にもいくつかのモチーフが彼女が娼婦であることを示しています。まず、裸でベッドに横になっているにも関わらず、アクセサリー類はきちんと身につけ、サンダルをつま先に引っ掛けているところ。
メイドが持っている花束は、彼女のお客さんからの贈り物です。
部屋の調度品なども、当時の様子を知っている人が見れば、いかにも・・という風に見える雰囲気なのだそうです。
 足もとには毛を逆立てた黒猫。これは高ぶった性欲の象徴とされています。猫といえば すぐに、魔性・エロチック ということになるけれど、必ずしもそうとは言い切れないのでは?とも思いました。
足もとには毛を逆立てた黒猫。これは高ぶった性欲の象徴とされています。猫といえば すぐに、魔性・エロチック ということになるけれど、必ずしもそうとは言い切れないのでは?とも思いました。
しかし、ティツィアーノのヴィ−ナスの足もとには丸くなって眠る子犬が描かれていて、こちらが従順の証とされていることに対比すると、たしかに興奮気味の黒猫は、高ぶる感情を想起させるものかもしれません。
集中非難をあびながらも、一方では、マネこそ新しい時代を創る画家とも評されました。今を生きる人々を描く、というのがマネの基本姿勢であり、それは美術史のなかで現代まで続く流れの源を作ったと言えます。マネが近代絵画の父と言われる理由のひとつです。
 日本で一番有名なマネの絵は「オランピア」ではなく、おそらく「笛吹きの少年」ではないかと思います。多くの教科書に載っているからでしょうか。
日本で一番有名なマネの絵は「オランピア」ではなく、おそらく「笛吹きの少年」ではないかと思います。多くの教科書に載っているからでしょうか。
娼婦のオランピアは、日本の教科書には載っていないかもしれないけれど、所蔵されているオルセ−美術館内ではいつも注目を集めています。ひとりで広いスペースを与えられ、特別な待遇を受けているようです。
マネの死後、オランピアがアメリカに渡りそうになった時、あらゆる手を尽くして国外流出を食い止めたのは、印象派の画家たち・とりわけモネだったそうです。
発表当時は叩かれたこの絵も、今ではフランスの宝です。歴史を辿ることの面白さは、 その時代を生きていた人々は知り得なかった未来を、時間を超え 一連の流れとして掴める点にあると思います。
130.5×190cm 油彩 オルセー美術館所蔵
*関連する記事:オルセー美術館のおすすめ作品
▲絵のはなし トップに戻る
おすすめの記事
▲このページの上部に戻る




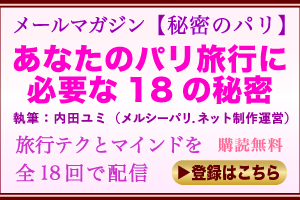
 サイト内検索
サイト内検索