スポンサードリンク
ジョルジュ・ド・ラ・トゥールについて Georges de La Tour
 「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」(1593-1652)は、フランス・ロレーヌ地方のヴィック=シュル=セイユという街で生まれました。
「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール」(1593-1652)は、フランス・ロレーヌ地方のヴィック=シュル=セイユという街で生まれました。
17世紀前半、画家として成功を収め、人気も得ていたようですが、その後この地方を襲った災害や戦乱により、作品の多くが失われ、画家本人の軌跡も途絶えてしまいました。
20世紀になって作品が再発見されたものの、画家の生涯についても 作品についても、不明な点が多く残されています。宗教画や風俗画が多く、中でも宗教画は精神性の高さを感じさせるものですが、画家自身の普段の行いはあまり評判の良いものではなかったようです。
ジョルジュ・ド・ラ・トゥールのこのような略歴を聞くたびに、私は別の有名な画家を2人連想します。
一人は、生前一定の評価を得ながらも、没後に一旦美術史上から姿を消し、約200年経ってよみがえった「フェルメール」です。
一度は歴史の影に隠れ、現代になってその作品が注目を浴びている点、室内に少ない人物を配した作品のイメージが似ていると感じます。
もう一人は、イタリア・バロックの天才「カラヴァッチョ」です。劇的な光の効果によって闇に浮かびあがる人物像。ドラマティックでストーリー性を強く感じさせる作品は、カラヴァッチョの作品に通じるものがあると思います(実際に、影響を受けているとされています)。
「作品の神々しさとは裏腹な画家の素行」という点でも、カラヴァッチョが念頭に浮かびます。カラヴァッチョほど激しくはなかったと思いますが。
日本人はジョルジュ・ド・ラトゥール好き?
ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの現存する作品は極端に少なく、残った作品にはキリスト教的宗教観をベースにしたものが多いのですが、その割りに、なぜか日本でも人気のある画家です。
2009年春に、東京上野の国立西洋美術館で開催されていた「ルーヴル美術館展」では、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール作「大工のヨセフ」が注目の作品として大きく扱われていました。
遡って2005年春には、同じく国立西洋美術館で「ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展」が開かれています。ラ・トゥールの代表作「いかさま師」が発していた強い存在感は、今でもよく覚えています。
故郷「ヴィック=シュル=セイユ」には、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの美術館があります。フランス人でも、特に美術好きな人でなければ訪れないというその静かな美術館に、日本人は団体でやって来て、来たと思ったら あっと言う間に去って行くそうです。(以前、NHKラジオフランス語講座のフランス人講師が話していました。)
謎めいた人物像が、何か人を惹き付ける要素のひとつになっているのかもしれません。
ジョルジュ・ド・ラトゥールの展示室(シュリー翼3階)
 ルーヴル美術館には、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品が6点あります。
人気作品が集中するドゥノン翼ではなく、比較的すいているシュリー翼(しかも3階)に、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの部屋が設けられています。
ルーヴル美術館には、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品が6点あります。
人気作品が集中するドゥノン翼ではなく、比較的すいているシュリー翼(しかも3階)に、ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの部屋が設けられています。
おそらく落ち着いて見学できると思いますので、ぜひ行ってみて!
| 【 展示室の様子 】 | |
 |
 |
(1642-1644頃) |
(1640年頃)
|
(1649年頃) |
(1640年代) |
(1635年頃) |
 |
 |
| 能面のような白い顔。この目つき・・。 | 何やら怪しい手の動き。豪華な衣装。 |
▲絵のはなし トップに戻る / ▲ルーヴル美術館のおすすめ作品 に戻る
おすすめの記事
▲このページの上部に戻る


 灯火の前の聖マドレーヌ
灯火の前の聖マドレーヌ 大工聖ヨセフ/Saint Joseph charpentier
大工聖ヨセフ/Saint Joseph charpentier 聖イレネに介抱される聖セバスティアヌス
聖イレネに介抱される聖セバスティアヌス 羊飼いの礼拝/
L'Adoration des bergers
羊飼いの礼拝/
L'Adoration des bergers  ダイヤのエースを持ついかさま師
ダイヤのエースを持ついかさま師


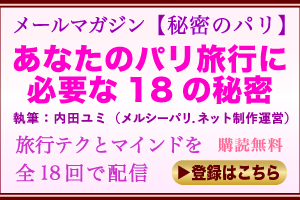
 サイト内検索
サイト内検索